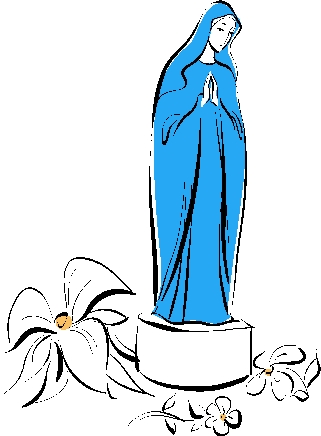| 2011.5.14〜5.19 |
| 5月14日(土) 仏法僧という鳥が居る。鳴き声からのみ言っていると思っていたら、今日読んだ仏教解脱の中に、仏法僧というのは仏教が述べる三宝のことだとあった。仏は仏様のこと、法は仏様の教え、そして層は仏にすがる人たちの集会のことだという。仏を信じ、その情けにすがり、その情けに忠実に生きる人たちがつくり出すのが和合だというのである。 十分にキリスト教にあてはめて考えてみることができる。三つの宝を大切にして教会をつくっていけば、世界の平和が生まれる。信仰に生きる人たちは、平和をつくり出していかねばなるまい。 |
||
5月15日(日)
|
||
| 5月16日(月) ナミュール・ノートルダムのシスター二人に夕食に招かれた。マンションに住んで教会に奉仕する姿は、新しい形での修道生活のあり方である。多くの人が集まって大きな業をするという形態から、小さく貧しく生きるという修道生活は、今の修道会を下から変えていくかもしれない。大きな事業を抱え、社会的地位を獲得して宣教するのと、少し異なっている。
|
||
| 5月17日(火) 桜町教会の婦人たちと雑談している中に、あるインスピレーションがひらめいた。先の日曜日、ルルド祭の中で仙台教区視察の報告を行ったが、その最後に物的支援のことについてふれた。この2日間で5通のメールが届き、具体的にはどうするかと問い合わせてきた。驚きと同時に、どうするかという戸惑いも覚えた。自分は今、後数日で司教館を去っていこうとしているのに、新しい仕事に着手できないという戸惑いである。M女子曰く、「サポートセンターを高松に立ちあげたらどうでしょうか」。これはまさしくひらめきである。被災地でない所にサポートセンターを立ち上げることは、思いつかなかった。これならやれそうだと心から思った。幸いにレナト神父も一緒にいて、センター長を引き受けてもよいとのことであった。さっそく教区の人々に知らせる原案書を書き始めた。四国の一隅から世界を照らす運動が始まることを期待している。 |
||
5月17日(火)
|
||
| 5月18日(水) 多くの慰労のメッセージが届いている。「去るものは日々に疎し」――。淡々と去ることが大切だ。そしてまた、次の課題に向かって歩む情熱と。過ごしたこの日々、悔いはない。しかし口惜しさは多分に残る。まだ無常の真価を悟っていない。凡人の域を出ていない自分がある。 |
||
| 5月19日(木) 事務所の女性職員と昼食を共にする。7年前事務局長と司教を兼ねて行っていた頃を思い出す。やはり難しい時代であった。知らない土地で知らない現場に突然投げ込まれると戸惑いがあるものだ。事務局長の一番大きな仕事は文書を作成し、議事録をまとめ整理する役割がその一である。同様に司教の意向を受けて教区の動きを活性化して行く役割がある。彼を補佐するのが教区会計である。司教、事務局長、会計の三役がうまくつながっていれば、どんな困難も乗り越えられる。どれかが突出すると、足並みが乱れて実りが少ない。司教を悪役にしないために、司教総代理の役割がある。司教が留守の時も、総代理を入れて三役が機能していれば、教区は万全である。 |
||