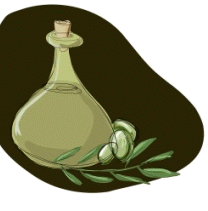| 2011.4.17〜4.23 |
| 4月17日(日) 小豆島教会でミサをたてた。小さな教会だが、よくまとまっている。一人一人が自分の役割をしていて、生き生きしている。羨ましいほどの教会である。高山右近像の建立、右近祭の開始、高槻教会との交わりなど、私にとっても想い出多い教会である。実にこの7年間で6名の司祭が代わって担当した。それが良かったのかもしれない。 夕方、氏家神父の別れの宴を開く。この1年半、短い間ではあったがよく働いてくれた。特に青年達とよく交わってくれた。大きな体でゆさゆさと歩く割にはタフで元気があった。災害の仙台でよい働きをしてくれることを期待する。 |
||
| 4月18日(月) 東京カトリック神学院で今年度初めての授業。宗教改革とトリエント公会議という目まぐるしい16世紀から問題を説き起こした。さらに、イエズス会の誕生と聖フランシスコ・ザビエルの来日、日本での初期宣教というところまで、一日4時間の講義をやり遂げた。 今年は日本の神学校には11名の新入生が入った。召命がないないと言いながら、やはり司祭職への道を歩みたいという青年はいるものだとつくづく思う。授業に与り丹念にノートをとっている彼らの姿は、日本の教会にはまだ希望があると感じさせる。来年は高松教区から2名入学の予定である。 |
||
| 4月19日(火) 聖週間に入り、5つの説教を準備しなければならない。毎年復活祭までの1週間は説教をどう準備するかで頭を悩ませる。毎年同じ聖書の箇所、同じ典礼で説教を考えるのはなかなか難しい。今年でこれももう終わり、来年からはゆったりとした聖週間を送ることになろう。嬉しいことである。司教になったからこそ分かった典礼が多々あった。これは恵みであった。やはりよく考えられている典礼で、典礼暦年に合わせた聖書の朗読は、私たちを豊かにしてくれている。今日は塩江のマンションに一日籠って、5つの説教を書き上げた。やればできるものだと少し自慢している。 |
||
| 4月20日(水) 聖香油のミサ。教区の司祭が集まる日であった。教区の殆んどすべての司祭が集まった。司教への従順ということを強調して話した。司祭達もそれを認識してくれているだろう。この教区に今こそ必要なのは、司教を中心とした教会づくりであろう。自分の特徴を主張している限りにおいて、一致も再生も生まれない。
|
||
| 4月21日(木) 部屋の片づけがほぼ終了した。シスター中島が丁寧に衣服をたたんで整理して下さっている。去っていく実感がある。仙台を去る時も、高橋夫人が同じように丁寧に整理してくださった。彼女は今どのように過ごしているのか気になっている。もし私が仙台にそのまま残っていたら、復興に向けて先頭に立って走っていたことだろう。それに比べて全てに恵まれて今を生きている自分が、恥ずかしくもあり致し方ないという無常をも覚える。私が使っているプリウスを仙台教区に贈った。多分司祭達にとって一番の良い贈り物になり、司祭活動の助けになると思う。司祭ボランティアに行きたいが、ガタが来ているこの体では反って迷惑になるのかも知れない。無性に仙台教区のことが想われるこの頃である。 |
||
| 4月22日(金) 陸前高田の高橋さんから、大船渡教会の信者さん5名が津波に流され亡くなったとのメールが入った。故郷がまるで変わってしまったとも言っていた。私は平和の中にあって想像だにできない。仙台のサポートセンターより、高松から車で来るなら釜石に行くようにとの指示があった。何時間の旅になるだろう。私は5月9日東京神学院で授業があるので、同乗して釜石に行こうと決めた。遠野教会、釜石教会の懐かしい人たちに会えると嬉しい。そして彼らが一番必要としていることを聞いて、高松に戻ることにしたい。 |
||
| 4月23日(土) パウロ神父主導で、この三日間朝の祈りを行っている。ゆっくりと詩編を唱えて、自分が感じることを祈りに代えている。すばらしい朝の祈りとなっている。深く黙想することを学ぶ、これが今の日本の教会にとって一番大切なことだ。「主は二日目に私を生き返らせ、三日目に私を立ち上がらせる」(ホセア5章)と朗読された。よく考えてみると、何かが分かって来た。アシジのフランシスコが病床から目覚めた時、神は彼を立ち上がらせ、人々の中に遣られた。パンプロナ城で負傷した聖イグナチオを神は目覚めさせ、マンレーサに送り込み、イエズス会創立の契機となった。比叡山に上った親鸞は阿弥陀の微笑みに会い、決意して山を下り人々の間に生きた。復活の喜びは一人だけに留めていてはいけない。聖堂を出て、その喜びを人々に伝えないといけない。 |
||