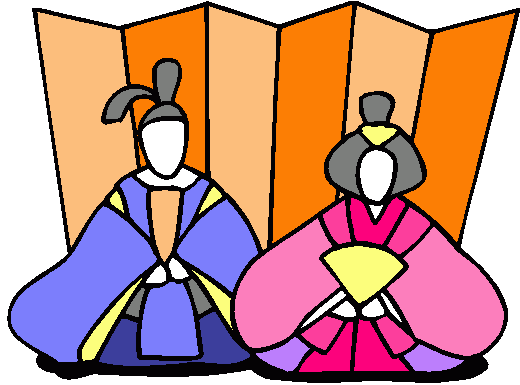| 2011.2.27〜3.5 |
| 2月27日(日) Y君とY子が訪ねて来てくれた。若い二人を見ていると微笑ましい。一緒に大歩危を通って祖谷温泉に行った。大歩危峡の流れは、春の日射しを浴びてきらきらと輝き美しい。古代の昔から、こうしてこの川は流れてきたのだろう。小石を水面に投げて一時を楽しむ。 |
||
| 2月28日(月) Oさんより便りを頂いた。一致が生まれないのは各人が自分の福音をふりかざしているからだと言う。自分の福音をふりかざし、正義の剣を振るって人をバサバサと切っていく、西部劇か時代劇の主人公のようになっている。これが不一致の原因であると言う。まさにその通りである。キリストの福音をしっかりと読みとることから、真の一致が生まれるのだ。福音をしっかりと読みとらない人が剣を振りかざしているところに問題があるとOさんは指摘する。人をまったく批判せず、福音を語るOさんの口調に深く感動した。福音を読むときのように、手紙を頭上に掲げて、丁寧に封筒にしまった。清々しい朝を体験した。Oさんに感謝 ――。 |
||
| 3月1日(火) 今日、司祭評議会と経済問題評議会の二つが開かれた。教区の財政は危機的状況にあり、普通の企業なら破綻している。宗教法人はお布施に頼っていて、それは予算の段階では全く予測がつかないのである。人々の心とこれまでの牧者的配慮によるのだから。2010年度の決算では2人の方の大きな寄付があって、バランスを保った。2009年は深堀司教の遺産で助けられた。2011年はどうなるのか。信仰という視点、司牧という視点をぬきにしては、教区の財政は語れない。計算して財産を切り売りし見事な決算をつくるより、神の摂理に信頼して一年一年をどうにか生き抜く方が信仰者の体質にあっているのかもしれない。 |
||
| 3月2日(水) 司祭評議会で新求道共同体「道」に話題が及んだ。「道」が問題なのでなく、教区の一致を妨げる運動になっているところが問題なのだという。それは「道」だけでなく、全ての司祭、信徒にもかかわる問題でもあろう。今、教区は協力宣教を推進している。これは第二バチカン公会議の教えであり、日本教会の基本方針である。協力宣教を実施するためには、小教区の壁を乗り越えなければならない。司祭間に緊密な連絡と信頼関係が必要だし、しっかり話し合ってどんな教会をつくるかという共通の理解を持つことが大事だ。「道」の人びとの問題をきっかけに、教会のあり方をあらためて見直すことができたのは、恵みと言ってもいい。教会のあり方をもう一度しっかりと見直し、真に福音的な教会づくりを真剣に考える時が来ている。 |
||
3月3日(木)
設計士村上晶子女史が来高。神戸中央教会、イグナチオ教会、鹿児島カテドラルといった大きな聖堂を設計した才媛である。東京サレジオ学園の総合設計をして頂いたころからのつながりである。桜町教会には阪神淡路大震災で被災した中山手教会のステンドグラスがそのまま使われている。残念なことに、窓の大きさの五分の四しか埋めることができず、後の五分の一とは趣が違っていて違和感がある。村上女子にこの違和感をなくすにはどうすればよいのかサジェスチョンをいただいた。下の部分を作製した盛岡の渡辺氏に依頼して、村上女史の監督の下に完成させる予定である。 これは私がここに残すことができるものとなるだろう。 |
||
| 3月4日(金) 来年度の東京カトリック神学院での授業準備に追われている。16世紀の宗教改革に始まり、トリエント公会議とカトリック教会の刷新運動、日本の宣教の開始と聖フランシスコ・ザビエルの生涯とその宣教理念、彼を継いだ宣教師たちの宣教への想いをまとめている。初期宣教時代、どれ程宣教師たちは試行錯誤したことだろうか。その実りを受けている者として、頭をたれる。 |
||
| 3月5日(土) 3月6日付けのカトリック新聞の「異見意見」の欄に、「道」についての一文が載っている。問題を的確につかんだ意見である。2週間前の岡田大司教の記事と合わせて読むと、「道」の何が問題なのかをはっきりと分からせてくれる。「道」関係の人たちがこれらを読んで、賢明に行動してくれればと願う。 |
||