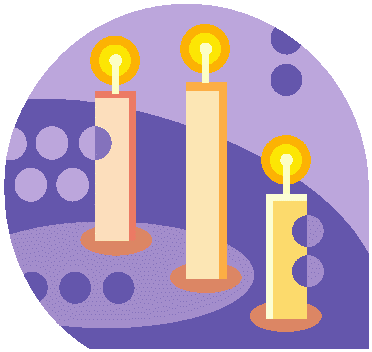| 2011.2.2〜2.11 |
2月2日(水)
|
||
| 2月3日(木) 早朝ホテルを出発、9時にカテドラルでミサが行われた。ロサレス枢機卿が司式、私が英語で説教した。落ち着いた良いミサであった。フィリピンの人々が思い切り歌う聖歌が、聴いていて気持ちが良かった。枢機卿は78才であり、次の司教を待っているという身につまされる話をしておられた。巡礼団の人々に、非常に親しく声をかけてもくださった。子供の頃、日本人から聞いたという日本語を、二言三言話しておられた。 その後、パトカーに先導されて、ディラオ地区にある高山右近像に献花するセレモニーに急いだ。思いもかけず、軍楽隊の演奏と女子学生の一群に迎えられての献花式となった。マニラ市長とゆっくりと行列、献花後、5分間の黙祷、ついでプレゼントの交換・・・。こんなことは想像もしていなかったので何の準備もしておらず、思いつきの挨拶となった。あちらの人々は日比交流の機会と考えてくださっていたのだ。 昼食は市長代理の女性と行う。彼女の父親は1570年代のマニラ市長であったという。優雅な女性だった。夕食はマニラの補佐司教パビリオ師と。パビリオ司教はサレジオ会員であり、神学院院長であった頃からの知り合いである。シスター前田のピアノ演奏で夕食会を楽しむ。大塚司教の挨拶とパビリオ司教の答辞、これも日比交流の一場面である。フィリピンの教会と日本は深い関係があった。今からもそうあってほしいものである。皆、喜びに包まれて床に就いた。
|
||
| 2月4日(金) 高山右近の遺骨があるというマニラ郊外のイエズス会修道院に向かった。元サント・トマス大学の教授であったデ・ペドロ氏の話を聞く。右近の遺体は聖アナ教会に葬られ、イグナチオ教会が新築された時にそこに移された。イエズス会が解散された間に、イグナチオ教会が崩壊、イエズス会は再開後、第二イグナチオ教会を建築した。その地下聖堂に、フィリピンで働いた歴代の管区長の遺体とともに、右近と内藤如安の遺体も移された。しかし、第二次世界大戦で教会が破壊され、地下聖堂に貧しい人々が住みこんだので、墓を荒らされることを恐れたイエズス会員達は棺を会の修練院に運んだ。そして "not known to people, but to God" という銘がある墓に葬ったという。中には赤いリボンで包まれた骨があるとデ・ペドロさんは言う。 司教の権威でもってしか開くことができないので、そのまま残しているという。しかし、この墓の前には絶えずローソクの火が燈されていたらしく、黒いすすが一際目立っていた。種々の事情を聞くにつけ、その蓋然性は高い。一度マニラの枢機卿と相談して、墓を開ける必要があるだろう。サンボアンガ教区の司教レデスマ師が、これについて一文を残しているという。そのコピーをデ・ペドロ氏に願う。大いなる希望の持てた墓地訪問となった。嬉しい嬉しい訪問であった。 墓地で右近の聖成のコンセプトをもとにして、黙想と祈りの集いを開く。30分くらいの集いは実り多かった。やはり公式巡礼の意義はこのあたりにある。
デ・ペドロ氏は、初めは市の国際交流局の職員であった。その頃、高槻市とマニラ市が姉妹都市になり、彼が高山右近という人物を知る契機となった。高山右近をナカヤマと間違えるほどトンチンカンな国際交流員であったという。しかし、高山のことも調べろという命令で、東京のチースリック神父と交流を持つようになった。彼は経済学部の出身で、史学科ではなかったが、すぐに英国に飛び、British Library で文献調査をすることから始めた。ついでマドリッドの文書館、ローマのイエズス会文書館に通った。こうして右近についての知識を深めることになった。その頃、チースリック神父はローマへの申請書を執筆中であった。彼の依頼でマニラに於ける右近の事跡について研究することになった。 先日亡くなった西本神父はマニラに残された右近の遺体について興味を持っていた。ことが成就する前に、大切な人々はいなくなるのである。結城神父然り、チースリック神父然り、西本神父然り ― 。 |
||
| 2月5日(土) セブ行きのフライトが2時間遅延。コンピューターが故障して手書きの搭乗券が配られた。遅くなったので、バスの中で弁当を食べた。サントニーニョ教会でのミサは、大勢の侍者がつく荘厳なミサとなった。ミサ中、仙石むつ子さんの洗礼式を行う。巡礼中の受洗は今回で3人目である。巡礼を充実させれば良い宣教の機会となる。最後の食事は、お別れと仙石さんの洗礼祝いとなる。最後の日でもあり、ラウンジで数人でウィスキーを飲む。楽しい一夕! |
||
| 2月6日(日) 帰国。氏家氏とソン神学生が関西空港まで迎えに来てくれる。司教団の公式巡礼として成功だった。参加者の方々もとても喜んでくださった。大切なのは、旅をすることよりも、どのような旅をするかだ。 旅の間、山田無庵の『千利休』を読み始める。面白い本である。右近を追っているうちに、茶道とキリシタンについて学ぶ必要を感じている。幸いに巡礼者の中に裏千家の師匠がおられたので、多くを聞くことができた。恵まれた! この巡礼で歴史を臨場感をもって実感する必要を説いた。400年前の人物を、彼らが生きたその場所においてみて、彼らが求めたものを肌で感じとることである。 |
||
2月9日(水)
|
||
| 2月10日(木) 岡山大学での講演が、文学部30周年記念講演シリーズとして出版されるというので、この三日間原稿の見直しをしている。見直している中に、内容が結構時宜にかなっていると思えてきた。西洋文化と宗教を分離しないまま日本に持ち込んだつけは大きかった。その時代にはその時代のmens(ものの見方)があるのだろう。しかし現代においてまで、宗教と文化を一緒くたにして他の国に宣教するなどといった愚は、くり返してはならない。 |
||
| 2月11日(金) キリシタン時代、教会の指導者は人材の育成に何よりも力を注いだ。その育成方法を見ると、日欧双方の文化を学ぶところから始まっていることに気づく。遠道であっても、日欧の古典の学習を大事にした。古典がわかるためには、フランス語、漢文の素養が何よりも大事と考えて、それに長い年月をあてた。日本の教会は、修道会も含めて人材の育成には時間がかかること、お金が必要なことを再確認する必要があるのではないか。即席の司祭は、宣教の真の原動力にはなれない。 |
||