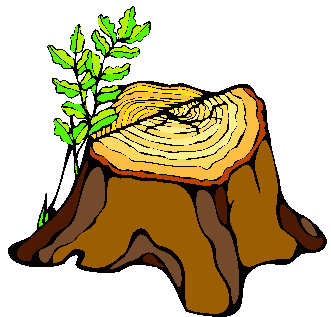| 2011.1.22〜1.29 |
| 1月22日(土) 坂出マルチン病院修道院聖堂で、一致祈祷集会が行われた。参加者50名程度。カトリックとプロテスタントとの間の亀裂を深めた問題「義化」について話した。聖書を素直に読んでいくと、「義」という意味がはっきりしてくるし、何によって救われるかが見えてくる。ルッターが主張したことには、一理以上のものがあるし、更にカトリックが強調した「ことばより行いを」という意味もはっきりしてくる。昔、「義」ということで争いになり、分裂したことが不思議でならない。今は「義」という解釈を通して、二つの教会の一致が促進されていくのを見ると、これも不思議でならない。これがわかるためには、これだけの歳月が必要だったのか。 |
|
| 1月23日(日) エキュメニカルのミサをカテドラルでたてた。幸いに書簡がコリント教会宛ての手紙であり、コリント教会内の分裂について書いてある。 パウロ派と自称する人達は、教会の枠を取り払って社会に開こうとしたグループだっただろう。アポロ派という人達は、教会の伝統と内部の一致を標榜するグループだったかもしれない。どんな教会をということで、2つの路線が争っていた。これに加えて、エルサレムから来たユダヤ人のグループは、ペトロ派と称して我こそは正統な教会と自負した。もっと悪いことは、こんな争いにうんざりして、自分はキリストを信じればそれで十分というキリスト派がいたことだ。 今、高松教区は「再生と一致」に向けて、どんな教会でありたいかという問題提起を掲げている。2000年前のコリント教会とは規模が違うにしても、信者同士の中でも、教会のイメージ、ひいては概念に食い違いがあることは間違いない。これを乗り越えて一つの教会をつくるのは、やはり困難が多いだろう。
|
|
| 1月24(月)〜25日(火) 大分教区司祭総会に招待されて延岡に来ている。司教不在ではや3年経とうとしている教区である。それにしても、司祭達が心を一つにして教区設立50周年の企画を真剣に話し合っている姿は好ましい。高松教区も早晩司教不在になる可能性もある。大分教区のように、その状況を乗り越えていけるだろうか。司教がいないと教区がないというのは甘えの体質なのかもしれない。多くのことは、心配しなくても成っていくと理解するのは、ぎりぎりまで追い込まれて腹を据えない限り、到達できないものかもしれない。 |
|
| 1月27日(木) 頬凍てて 子の帰り来る 夕餉哉 (子規) 明治32年(1899)の子規の句だ。今日は頬凍てる夕だ。100年前も今も変わらない家庭の風景であり、微笑ましい。頬を真っ赤にして、ただいまと帰る子供、家に入ると夕餉のにおいがあり、母親が寒かったねと子供の手を包む。一句だけでもその情景が美しく広がっていく。 |
|
| 1月28日(金) 先週NHKBSで「Hearts and Minds」を観る。以前から一度観たいと思っていた映画であった。こういう映画が上演されることのない地方都市に住んでいるので、知ってはいたがついぞ観る機会がなく、今回は有り難かった。 ベトナム戦争で傷を負った元戦士たちの証言をもとに作られている。多くの映像はリアルで、そして悲しい。それ以上に、国家をあげて英雄視しようとする戦争とその悲惨さは眼を覆いたくなるくらいだ。種々の形で存在する正義の名の下に、どれ程の血と涙が流されて、多くの人間の生涯がズタズタに引き裂かれるのかも分かった。 戦争はしてはいけない。戦争にならないために、毅然とした国づくりを考えないといけない。 |
|
| 1月29日(土) 岡山大学文学部30周年の文化講演シリーズに呼ばれて講演する。国立大学でキリスト教について話すことはすばらしいことだ。「キリスト教と日本文化―受容と拒絶」というテーマで話す。皆良く聴いてくださり、また多くの質問が出る。とても良い雰囲気であった。聴衆にはインテリが多かっただろうと推察する。 宣教は多面的に考える必要がある。今日本のカトリック教会は、知的面での宣教を大切にしているだろうか。カトリック教会外でも、自由に発言できる人材にかけているとすれば、憂うべきことである。カトリック大学の責任は重大である。カトリックの中高も一流大学に通した後のフォローを考える必要がある。 |
|