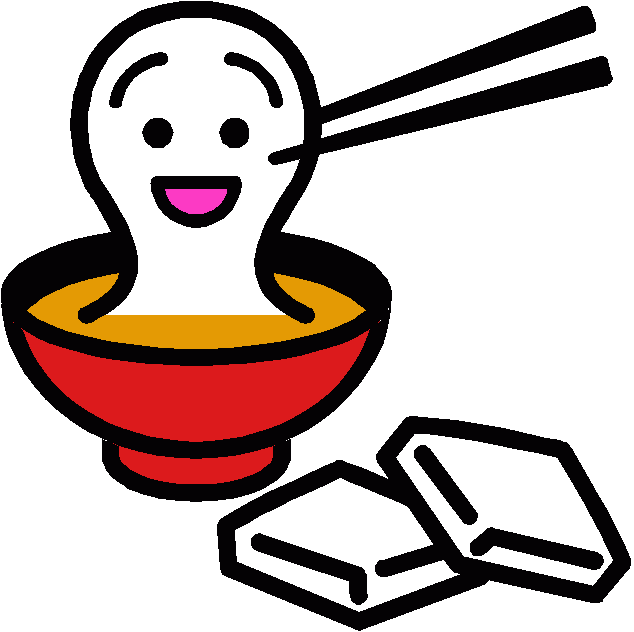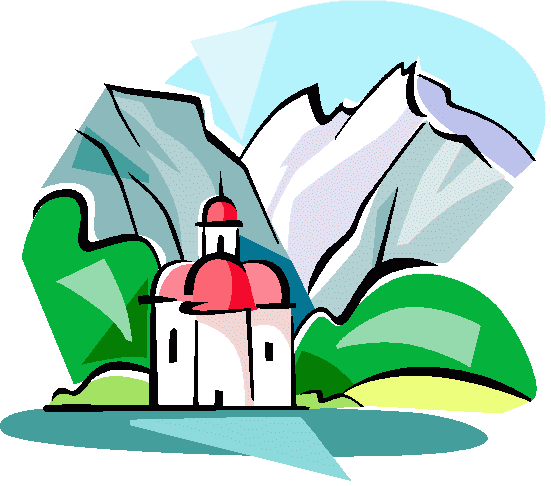| 2010.12.30〜2011.1.11 |
| 12月30日(木) 「文革時代」をNHKで観る。群衆を駆り立てていくその方法は恐ろしい。民衆を扇動して一つのことを成し遂げていく巧妙な指導者達。そして、ますますエスカレートして暴力を振るっていく民衆。一度理性が狂うと、行きつくところまで走り出すものだ。そのいずれも、ある人を偶像のように祭り上げることに始まり、それで一致を保ち、狂気の沙汰に追い込む。新興の宗教の多くが教祖崇拝から始まっていることにも、同じことが言える。教祖が言ったことをオウム返しに繰り返すようになると、恐ろしい結果の始まりである。揚句の果てに、紅衛兵が派閥に分裂したように、ある人を偶像化すると、路線闘争が起るのは必至だ。70年代の日本の学生闘争にも、全く同じ現象があった。 |
||
| 12月31日(金) 炬燵を出してみかんを持ってくる。正月の用意はこれで完了。実に多くのことがあった年だった。ただ正しいとか不正だとかで争うことは愚であると、分からせてくれた年でもあった。すべては過ぎ去る。何の名誉も必要でない。徒らに大上段に構えると、空しさのみが残る。思いきってすべてを捨ててしまえばよい。半時間座禅を組む。一年がすべて過ぎたと思わせる一瞬間だった。「怨みつらみ」は乗り越えたい。 |
||
| 2011年1月1日(土) 2011年正月。やっと年賀状書きを始める。新年のあいさつを親しい人々に送る。あと少しで76才―いつ退職という喜びの知らせが来るのか。その時にはあれもしたい、これもしたいと思いを馳せる。これも浅薄なことだ。なるようになる。この気持ちに忠実であることの方が大切であろう。 キリシタン時代の典礼について語った。正月という日本の祝日を、どのようにキリスト者の祝いに取り入れようかという涙ぐましい努力があった。日本は陰暦であり、往々にして日本の三が日は四旬節にあたっていたとのことである。それでも、日本の教会は、四旬節、灰の水曜日を調整してでも、正月を優先させたのであった。400年前の宣教師達の見識は大したものである。結局は正月を「お守りのサンタマリアの祝日」としたのだ。 ついでながら日本の教会は、当時のヨーロッパの教会が聖人聖女の祝日やマリアの祝日を多く暦に加えていたのを全部排除し、救いの歴史に必要な祝日にしぼったのであった。私はこのような歴史を持つ日本の教会を誇りに思う。 |
||
| 1月2日(日) N家を迎えて夕食会を開く。午後から買い出しをして食卓を整えた。M師は、自分の若い頃、東京でイエズス会のヨヘル師が始めたセトルメントに多くの学生が集まり、下町の子ども達の世話をした、その時集まっていた青年の中から有為な教会の指導者が多く生まれたという話を出席者にした。高松司教館に集まっている青年達の中から、次代の教会を背負う人材が育つことを期待してやまない。食事はみな、司教館のスタッフの手作りである。和気あいあいの雰囲気の中で宴がすすんだ。ご両親も、高松塾に預けたことに安堵されたことだろう。最後に恒例のふり返りをして終了する。「道の聖母」を一緒に歌う。心地よい正月の宵であった。
|
||
| 1月3日(月) 「日露戦争はあの方式で勝ったというその国家概念が、本来軍事専門家であるべき陸軍の高級軍人の頭を占め続けた。」これが太平洋戦争の敗戦につながったと司馬遼太郎は言う。一つの方法で成功した時、それがどこでも通用すると思うこと、これは敗北の始まりである。「勝って兜の緒を締めよ」というのは、このことなのだろう。一つの方法が世界のどこでも通じると思うことも、その一例であろう。宣教には種々の方法を考える柔軟な頭脳が必要なのだ。 |
||
| 1月4日(火) サウンド・オブ・ミュージックを寝転がって見る。美しいオーストリアの山と湖だ。若い頃、ドイツ語を学びつつボーイスカウトの子供たちとアルプスに登った。マリアンゼーでの湖上の祈りの集い等が想い出された。初ミサの時は、参加者一人一人に按手して祝福を与えたことで疲れ切ったのも、よい記憶としてのこっている。エーデルワイスを採ったのも、その頃のことだ。オーストリアは美しい国だ。少し感傷的になっているのかもしれない。
|
||
| 1月5日(水) 私の休みの最後の日、朝よりMISIAの"Every Thing"を数度聴いている。良い歌だ。歌唱力がないと歌えない。時代が移ってもやはり良い歌が生まれるものだ。 今日は底冷えがする。香南町のシスターの朝ミサの時は気温1度であった。春夏秋冬、夫々の持ち味を生かして日本を豊かにしてくれている。これは天の恵みである。 T君帰院。晴れやかな顔をしている。静かな正月を送ったのであろう。夫々の正月、夫々の過ごし方、それで良いのだ。 |
||
| 1月6日(木) 神戸愛徳学園で、全職員の研修会の話を頼まれた。マルコ福音書の中のメッセージを取り上げて、カトリック学校に奉職する職員の資質について話した。もし私が管理職の校長であれば、どのような先生を望むか、というのが副題である。 まず、宗教心に基づいた謙虚ということをあげた。成果主義が横行する現代に於いて、天から与えられた使命として教職を生きることである。法隆寺の壁画に、子供を養うめすの虎の絵が描かれているそうである。食糧が尽きた時、母虎は自分の肉を食いちぎって子供に与えて、自分は死ぬということである。十字架につけられて死んだキリストを主と崇め、その生き方に学ぶ教会の者にとっても、この話は開眼であろう。共通点を仏教の中に見出すのは、案外容易に思える。 |
||
| 1月7日(金) 徳島でオブレート会の人々と昼食を交えて3時間過ごした。昨年暮れ、ローマで何があったのか、どんなことがあったのかを報告し、意見の交換を行った。地方教会と中央教会、この問題はいつも歴史の中で起ったことであったが、この小さな高松教区で現実に起こるとは夢にも思わなかった。地方教会はやはり自律心をもって、主張すべきことをきちんと主張して行く必要がある。そのためには「知られず、知らせず」の態度を改めて、きちんと起ったことを教区民に知らせることが大切であると、逆に司祭達から戒められた。本当にそうだと思う。 |
||
| 1月9日(日) 昨日ローマから出されているインターネットZENITに、「日本に於いて新求道共同体、『道』は中止されない」という記事が載った。12月13日の日本司教達とローマの高官との会談の内容というより、彼らが考えた結論を掲載している。正確に言うと、ベルトーネ国務長官が「日本司教団の結論は承認し難い」としたということであった。これは重大な発言であり、教皇様がそう発言されたならともかく、そうでない場合、地方の教会の自律性を完全に無視したことになる。 更に、特使を日本に派遣すると述べ、その特使は「道」を愛し(loves the Way)、司教達の問題も尊重する人であると付け加える。私は、そうではなくて、日本で起ったこと、起っていることを客観的に把握し、分析し、それを正確にローマに報告できる人のことを指していると思う。偏った人を送って貰っては、現場は困るのである。 私は、一つのグループと地方教会の司教達とを同列において対話を始めさせるのはおかしいと率直に思う。やはりその地方で働く人達は、地方教会のとっている路線に従うのが常道である。 |
||
| 1月11日(火) 司馬遼太郎『坂の上の雲』の一節を味わってみる。「加藤嘉明は晩年人から『どういう家来が戦に強いか』と聞かれた。当然強いと言えば天下に響いた豪傑どものことであるという印象がその当時の世間にあるが、嘉明は『そういうものではない。勇猛が自慢の男など、いざという時どれほどの役に立つか疑問である。彼らはおのれの名誉をほしがり、はるかなる場所ではとびきりの勇猛ぶりを見せるかもしれないが、他の場所では身を惜しんで逃げるかもしれない。合戦というものはさまざまな場面があり、派手な場面などはほんのわずかである。見せ場だけを考えている豪傑など、少なくとも私は家来としてほしくない。』戦場にほんとうに必要なのはまじめな者であり、たとえ非力であっても責任感が強く、退くなと言われれば、骨になっても退かぬ者が多いほど家は強い。」 今朝、司祭評議員全員でミサをたてた。新しい年のはじまり、この人達と教区を作り上げていくのだ。加藤嘉明ではないが、派手な戦場で武勲を求める仲間ではなく、死んでも退かぬ仲間を持つことが最大の恵みなのだ。 |
||