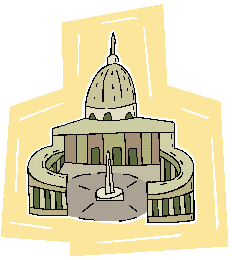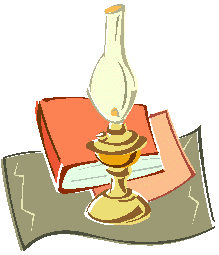| 2010.12.9〜12.16 |
| 12月9日(木) 「泣きながら良い方をとる形見分け」 不詳の作者の川柳である。どんな状況でも人間は欲深い。これが断ち切れた時が死なのか。死に際しても、人間の欲望をむき出しにすることが多いと聞く。人の中にうごめく欲望を抑えるのは困難だ。幼きイエスが手を差し出している姿に、ほっとする。
|
||
| 12月10日(金) 東北塾に参加する。盛岡は寒い。しかし、塾生は熱い。現代、教育を推進するには何が必要なのかと互いに熱く語り合った。「すがる」ことと「人々の間に生きること」この二つである。自分が自分がという教育ではない。自分の空しさを知った上で、人と接して行く教育である。1時間半の話を、よく聴いてくださった。 |
||
| 12月11日(土) 「甘酸是人生」 「皆共成仏道」 花巻で寄った高村光太郎の住居に掲げられている句である。甘さも酸っぱさも是人生。受けて立たねばならない。「皆共に成仏する道」、合掌して日々生活できると、幸せなのだろう。大上段に振りかざした宣教論に飽きあきしている。 |
||
| 12月12日(日) 司馬の『坂の上の雲』2巻まで読み終わる。明治の人達は国づくりに燃えていた。そして、明日にかけて生きていた。恥ずかしいことに、今私達は明日が見られない。くどくどとくだを巻いてダダをこねる子供に似ている。熱く人生を語る。こんな友と出会いたい。 |
||
| 12月13日(月) 夕方6時より8時まで「ボローニアの間」で教皇と6人の枢機卿を交えての話し合いがあった。どうして日本の教会のことについて、ローマの高官が介入してくるのかよく分からない。 流石教皇は話をよくまとめて下さっていた。日本の教会は閉鎖的で新しいものを受け入れない教会だというのだろうか。いや、日本教会は、聖霊が教会を刷新されることを信じ、多くの新しい運動を教会のために受け入れてきた。私は自問自答している。ヨーロッパ中心の教会という視点を少し変えることも必要なのではないか。
|
||
| 12月15日(水) ローマからの長い旅を終えて、無性にうなぎが食べたくなった。東京駅の地下街で店を見つけ、舌鼓を打った。やはり日本人なのだという実感 ―。ローマで起ったこの二日間の出来事は、私の胸に、しこりのように刺さっている。 |
||
12月16日(木)
|
||