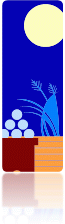| 2010.9.23〜10.1 |
| 9月23日(木) 深堀司教一周忌追悼ミサ 深堀司教一周忌追悼ミサあり。大雨の中で多数参列。私も司教職の終わりにあたっている中で想うこと多し。先輩の司教たちは、どういう想いで最期を過ごしたのだろうか。 午後、青年たちと岡山教会に行き、早副神父の金祝に参加。多くの功績があった神父だ。老いて尚、人望を失うことがない早副神父に頭が下る。司祭職を生き抜いた人には、全身からにじみ出る聖徳の香りがある。 |
||
| 9月24日(金) 湯布院にて 湯布院は寒い。豊後の団子汁をつくって食べる。故郷の味だ。こんなシンプルな食べものが好ましくなっている。1623年のイエズス会準管区長の書簡を読む。イエズス会がドミニコ会を軽視するといった訴えに対して、ローマに送った手紙である。 新米の宣教師は経験をつんだ人々に敬意を示し、その経験を借りなければいけない。経験を積んだ人々は、それを分かち合わないといけない。これは現代にも言えることである。 うたたねの わが胸に舞う とんぼかな |
||
| 9月25日(土) 山登り 九重硫黄山に登る。思ったより大きな噴出量だ。二時間余、息を切らしつつ登る。これが今の私の限界か。サンドウィッチを頬張り、山の空気を思い切り楽しむ。全ては過ぎ去っていく。しかし、ずっとそのままで居たい時間もあるものだ。 帰りに筋湯温泉に寄る。三軒自由に入れる湯屋を設けている。そのひとつに入る。打たせ湯があり、その上を青葉が広く覆っている。打たせ湯に合わせて、裸の尻が並んでいる。 打たせ湯に 青葉迫りて 人の尻 気だるさや 湯をかけて蚊を 殺したり |
||
9月26日(日) 月を見る
|
||
| 9月27日(月) 土砂降りの中、新宿のホテルに着く。ぬれた服を乾かし、風呂に入り、早めにやすむ。大都会の中の密室、物音一つしない不思議さ。 |
||
| 9月28日(火) 日本カトリック児童施設協会の全国会議に講師として呼ばれる。複雑な現代の養護やその組織については、皆目分からない。ただ、カトリックということばがついている限り、そこに流れている福音という理念に通じていかないといけない。 マルコの福音を使い、現代カトリック施設に働く人々が基本として納得して持っていてほしい考え方を話す。よく聴いて下さった。 また土砂降りの雨の中を空港に向かった。日下淳一郎が会いに来てくれた。高松塾に誘う。少しづつ高松塾が広がりつつあるのを感じる。 |
||
| 9月29日(水) 一時間余り散歩をした。「道の駅」に汁粉があって、それを食べる。もちが程良く焼けていて美味しかった。途中に栗が沢山落ちたままになっている。今年の休暇もこれで終わり。これを許してくれている仲間に感謝。 しとしとと降る雨に眠気をさそわれ早寝する。 |
||
| 10月1日(金) 高山右近巡礼の問い合わせあり。単なる旅行にならないように気を配る必要がある。 「社会と福音」の中の「戸田神父殺害事件」の執筆者佐々木氏より返報あり。歴史の見方、一つ一つの出来事を積み重ねて、その上で戦時中のカトリック教会のあり方を判断することが大切である。闇雲に歴史上の人を糾弾すべきではない。人は時代の枠の中で生きるからである。 内閣は揺れている。「党は一丸となって」などとモットーを口にしているが。日本存亡の危機にあるという危機意識が非常に薄い。これを憂う。カトリック教会もギリギリまで追い込まれている。千年一日の如く、ただ儀式に頼っていては発展しない。 |
||