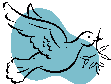| 2010.7.18〜7.24 |
| 7月18日(日) 「元気をだそう中高生ミサ」が高知の中島町教会で行われた。教会が若い人で半分は一杯になった。若い人というより、後ろ半分を埋めた若くない人を”元気にした”ミサであった。集めればこんなにたくさん人が集まるものだと感心した。まだ高松教区には若者が居るという喜びでもあった。 招待したサレジオ高校生達が、古典に近いラテン語の合唱曲を歌ったのは新鮮であった。典礼聖歌集のみにこだわっていて、いつの間にか、合唱で歌う聖歌の魅力を忘れてしまった感が最近はある。「messis quidem, orerarii autem pauci . . . 」など懐かしい歌の一つである。20代の青年であった私が、思い切り歌った歌である。典礼聖歌は抑えて歌うという指導を受けたが、腹の底から歌うと気持ち良いものだ。カラオケであんなに声をあげて歌う人たちが、教会では口を開けないのはどうしてだろう。
|
|
| 7月19日(月) 「Homo proponit, Deus disponit」(人は提案し、決定するのは神)。まさにその通りである。人は多くのことを計画し、提案する。その通りにことは運ばれると、思いこんでしまう。変転極まりないこの世界が、永遠に続くかのように錯覚している。般若心経の「色即是空」のこころを、理解していない証拠だ。万物は変転して滅ぶ。滅びゆく中にあって、無心の心を学ぶ。これが色即是空の心であろう。決定するのは神であり、その方の中にあるこの世に起ることは、その方に任せることだ。 小豆島で高山右近祭が行われた。これで四回目だ。変転きわまりない戦国時代を、志を全うして生きた武将である。美しいとは志を全うして生きる人のことである。そして、その人は志を守るからこそ、損を承知の上で、志を高くもつのだ。 |
|
| 7月20日(火) 先月、マルコ6章にある洗礼者ヨハネの殉教の場面を、聖書勉強会の仲間と読んだ。決断力のない男ヘロデ。そのくせお調子者で、踊りを踊った小娘サロメに、「この国の半分でもあげよう」と豪語する。たくましく、そして冷徹な女、サロメとその母。「洗礼者ヨハネの首を」と可愛い少女は言う。その母は斬られたヨハネの首を見て、その舌を針で刺したとの伝えがある。マルコは短く厳しく文を閉じる。「獄中でヨハネの首をはね、その首を盆にのせて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母に与えた。」冷たい女の性(さが)、右に左に揺れる男の性(さが)。見事な一幅の画だ。 オスカー・ワイルドの「サロメ」を読む前に、じっくりとマルコのこの箇所を味わってみたらどうだろう。ところが、先生イエスの奇跡で浮かれていた弟子たちは、この話を聞いても全く関心を示さなかった。不思議な物語である。 |
|
| 7月21日(水) 太宰治の本はかなり読んでいるつもりであるが、「新ハムレット」という短編があるのは知らなかった。これを教えてくれたのが、シスター今泉ヒナ子の「マザーについての独り言」という、カトリック生活誌の中の一つの記事であった。 太宰はマタイ16章13節から20節を、彼なりに解釈して説明している。この箇所では、イエスが自分の評判を気にして、弟子たちに、「皆はわたしのことを何と言っているか」と尋ねることから始めている。弟子たちは「洗礼者ヨハネと言う者もあり、エリアだと言う者もいます」と答えた。「では、お前たちはわたしを何者だと言うのか」とイエスは問いかけになる。太宰は、この質問をするイエスを、すっかり自信をなくした弱々しい男として登場させる。「弱気のイエスが、藁をもつかむ思いで弟子たちに頼ろうとする」という解釈をしている。ペトロが、「あなたは生ける神の子メシアです」と宣言することで、弱気のイエスにしゃきっとした筋金を与えたというのだから、何と言っていいか分からない。 それにしても、聖書をこのように読むと、また面白いということも悟らせてくれた。この位弱気なイエスを認めるのは難しいが、本当にそうであれば、もっと親しみやすい。人間の弱さを全身に見せるイエスを、「主」と呼ぶのに抵抗がなければ・・・。 |
|
| 7月22日(木) 組織にしがみついて生きる時、自由でない。組織を活かそうと努力して疲れ果ててしまう。自由に生きていると豪語する者は、その自由にしがみついてしまう。自由に生きるとは難しいものだ。
|
|
| 7月23日(金) 私は修道司祭である。修道者であることがその第一であり、その次に司祭という肩書きがついてくる。修道者は自分の修道会の使命にそって祈り、働く。その労働の糧で生活する。自分の使命を司祭として果たすのが、修道司祭である。修道司祭にとって、何をどこでということとその使命とを、分けて考えることはできない。どこに居ても構わないし、どんな職務を伝えられても構わない。しかし、基本は、どんな場にあっても自分の使命を生きることである。 私はサレジオ会員として、どんなに老いても、どんな場に生きようとも、青少年育成をまず第一とする生き方を全うすることである。 これこそ、カリスマによる生き方である。カリスマは形態を守ることにあるのではない。その人の生き方を支えるもの、精神なのである。その使命がはっきり分からないまま修道精神を説くならば、それは無意味である。 |
|
| 7月24日(土) 社民党党首のF氏は、「『選択的夫婦別姓』の定着はライフスタイルにおける自己決定権を持つことである」と主張する。ここまではなるほどと思ったが、そこから、「これによって、結婚、離婚はシンプルな行為になり、同性の結婚もあって当然。不倫による非嫡出児の妊娠や出産も守られる」とまで行くと、どうも納得がいかない。これが「多様な価値観が認められる望ましい社会だ」とF氏は論を進める。(広瀬一峰「『選択的夫婦別姓』推進論へのオブジェクション、福音と社会250号」 夫婦別姓がここまで問題をはらんでいる、とは知らなかった自分を恥じる。 |
|