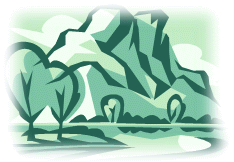| 2010.7.11〜7.17 |
| 7月11日(日) マルコ福音7章にあるフェニキア、ティルスの女の話を、マルチン・ルッターが好んで説教に引用したと聞いたことがある。疲れ切って、弟子たちの鈍さに少しうんざりして、引きこもろうとしていたイエスを引きずり出した女の話である。イエスは「パンを小犬にやるのはよくない」と不機嫌に言うのに対して、「小犬も食卓から落ちるパン屑を食べるのではないですか」とやんわりイエスをたしなめている。 カトリック教会が原理原則を主張し、組織体を固めていく傾向にあるのに対して、ルッターはこの個所を使って、宗教の本質を浮き彫りにしようとしたのであろう。いつの間にか、「まず教会のため、ついで他の人のため」と言ってしまいそうな体質を、私たちは持っているような気がしてならない。 |
||
| 7月12日(月) NHKの矢崎伸治さんと、高山右近について親しい語らいの時をもった。今回の高山右近列福の中核を理解するのに役立った語らいであった。 右近のキリスト教理解は日本の土壌、文化にしっかりと根ざしていた。ヨーロッパのキリスト教をそのまま持ち込むことには抵抗した。茶道と武士道という日本の二つの文化形態の中に、キリスト教を積極的に導入したのであった。あるいは、キリスト教が日本の文化を受け入れる態勢をつくるべく、一生努めた人が右近であった。 現代のカトリック教会が、その土地の土壌に根ざしたキリスト教のあり方を主張している割には、問題の大切さに目覚めているとは思えない。 * * * 今朝は大雨、しのつく雨とはこういうことを指すのか。全てを洗い流していくその勢いは、まさに自然の脅威である。その驚異の前に、頭を垂れることができるかが信仰の岐れ目である。人間の思い上がりを正すかのように降ってくる雨 ― 深い祈りに代えたいものである。 |
||
| 7月13日(火) 世界はワールドカップサッカーで湧いている。夫々の国旗を掲げて国同士が争っている感がある。その実、全力をぶつけ合って戦っている姿は清々しい。世界は平和であるとの実感がある。 しかし、これに参加していない国の人々は、これを見ても、なんの感動もないかもしれない。ともかく世界のサッカーファンとともに、せめて試合の熱気と清々しさだけは味わってもよいのではないか。相撲の世界が、野球賭博とかで薄汚く見えるのは致し方ないことか。 |
||
| 7月14日(水) 山本一博著「殉教」を読み終えた。殉教を強調する余り、為政者を刺戟しすぎた嫌いがなかったかと教会に問わねばならないといった結論である。確かに多くの点で行きすぎた殉教熱があったが、それとは異なって冷静にことを受けとめ、あえて信仰道を選んでいった人々が居ることも分かってほしい。殉教がでない国づくりということを考えている人達が居るが、そのため軟体動物の集団のような、ひょうひょうとした国になる可能性があるとすれば、赤信号を点じたい。
|
||
| 7月15日(木) 先週二、三日間図書館に籠った。高山右近関係の資料を、せめて自分の目で確かめたいと思うからである。机上の学問といわれるが、やはり、自分で歩いて確かめてみることで、その真実が見えてくるものだ。頭でっかちの説教者にありがちなのは、相手がおかれている状況をしっかりとつかんでいないということ、これである。 図書館に一日中座っていると、実にたくさんの人が出入りする。実にたくさんの本の読み方があるものと実感する。たくさん書類を持ち込んできて、次から次へとめくって読む人がいる。頁をめくる音がこんなに大きいのかと、分からせてくれる。昼寝をする人、もっとも、この私もその一人であるが・・・。くちゃくちゃとガムを噛みながら本を開いている人。扇子で風を送りつつ、眼鏡を鼻の上にのせて読書する人。飽きない光景である。男性の老人が断然多いのも、その特徴である。 いま、私は戦国時代の突入の頃の京阪の歴史を追っている。四国勢が歴史に光り輝いた時代であった。しかし、何度読みなおしても、政権交代の早さには頭がついていけない。その政権交代の中枢を占める場所に高槻は位置しており、高山右近の政治的困難がよく見えてくる。 |
||
| 7月16日(金) 先月比叡山に上った時、「白檀」を買った。今まではローソンで売っている香を使っていたが、流石「白檀」はその香りが違う。最近香りのみを喧伝して甘い線香が流行になっている。何とかセラピーの一種として使われている。私としては甘すぎて瞑想の場にはふさわしくないと思い、それをやめた。 「白檀」は自然の木の香りがする。しかも、ほんのりと甘い。とも角やわらかい香りであり、煙も遠慮しいしい上ってくる。私は今はこの香りを楽しんでいる。自然と宇宙のつくり主との間をさまよう私の魂のやすらぎの場に、豊かさを運んでくれる線香である。 |
||
| 7月17日(土) 現在は、ロペス・ガイ著「キリシタン時代の典礼」を読んでいる。深堀司教の蔵書の中にあったものである。 かなり難解で忍耐のいる本なのだが、彼は最後まで読み終えている。各頁に注を入れたり傍線を入れたりして、かなり集中して読んだことが分かる。茫洋とした風貌の中に、緻密な才能が隠されていると実感した。深堀司教が亡くなり、早一年が過ぎようとしている。神のみぞ知る深堀司教の魂の偉大さである。 |
||